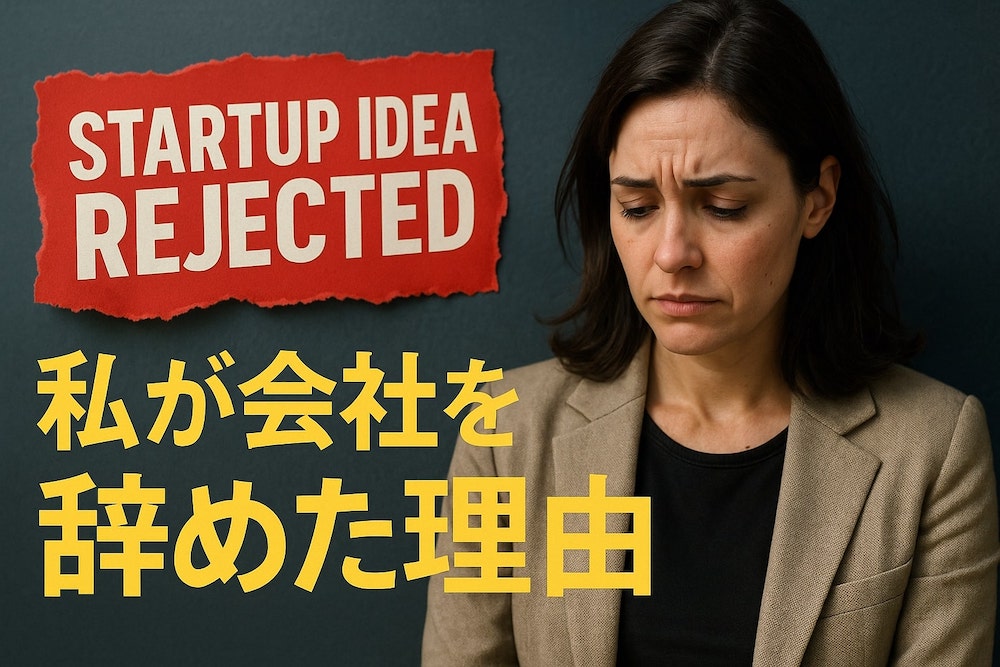
起業アイデアが通らなかった時、あなたはどうする? 私が会社を辞めた理由
「そのアイデアでは、難しいね。」
会議室に響いたその一言が、私の人生の大きな転換点となりました。
積み上げてきたサラリーマンとしてのキャリア。
安定した生活と、それなりに満たされた日々。
しかし、心のどこかで感じていた「このままではいけない」という想い。
その想いを託した新規事業アイデアが、あっけなく壁に跳ね返された瞬間でした。
この記事は、輝かしい成功譚ではありません。
むしろ、一度は“敗北”を味わった人間が、そこから何を学び、どう再出発したのかという、泥臭い記録です。
もしあなたが今、組織の中で何かしらの壁を感じているなら、あるいは自身のキャリアに迷いを抱いているなら、私の経験が少しでもヒントになれば幸いです。
これは、40歳を目前にした一人の男が、会社を辞め、自分の足で歩き出すことを決意した物語です。
リクルート時代:希望と苦悩の10年間
営業から企画へ、積み上げた信頼と成果
1989年、私は早稲田大学商学部を卒業し、株式会社リクルートの門を叩きました。
当時はバブル経済の絶頂期。
世の中は活気に満ち溢れ、私もまた、大きな夢と希望を抱いて社会人としての第一歩を踏み出したのです。
配属されたのは営業部門。
まさに「足で稼ぐ」という言葉がぴったりの、地道な仕事の連続でした。
お客様のもとへ何度も足を運び、頭を下げ、時には厳しい言葉をいただくこともありました。
しかし、そこで培われたのは、お客様のニーズを的確に捉える力と、何よりも「人との信頼関係を築く」ことの大切さでした。
数年後、営業で培った現場感覚と実績が認められ、企画部へ異動。
ここでは、市場の動向を分析し、新しいサービスや事業の種を見つけ出し、形にしていくという、よりクリエイティブな仕事に携わることになりました。
営業時代とはまた違うプレッシャーとやりがいを感じながら、数々のプロジェクトに関わり、それなりの成果も残すことができたと自負しています。
社内起業制度に託した“想い”
リクルートには当時、「New RING」という素晴らしい社内起業制度がありました。
社員が自ら新規事業を提案し、それが認められれば会社が出資して事業化できるというものです。
「ゼクシィ」や「ホットペッパー」といった、今や誰もが知るサービスも、この制度から生まれたと聞いています。
企画部での経験を通じて、私の中にも「自分の手で、世の中にまだない新しい価値を生み出したい」という想いが日増しに強くなっていました。
そして、温めていたアイデアをこの「New RING」に託すことを決意したのです。
それは、長年現場で感じてきた課題意識と、それを解決したいという純粋な情熱から生まれたものでした。
通らなかった起業アイデアとその理由
しかし、結果は「否決」。
私が提案したのは、当時まだ注目されていなかった地方の中小企業が持つ独自の技術やノウハウを、都市部の企業ニーズと結びつけるプラットフォーム事業でした。
今でこそオープンイノベーションの重要性が叫ばれていますが、当時はまだその概念も薄く、時期尚早と判断されたのかもしれません。
審査員からは、主に以下のような指摘を受けました。
- 市場規模の不透明さ: 「本当にそんなニーズがあるのか?」「どれくらいの収益が見込めるのか?」
- 事業の実現性: 「どうやって全国の中小企業の情報を集めるのか?」「マッチングの精度をどう担保するのか?」
- リクルートの既存事業とのシナジー: 「我が社が取り組むべき事業なのか?」
もちろん、指摘された内容はもっともなことばかりでした。
しかし、私の中には「それでも、この事業には価値があるはずだ」という確信にも似た想いがあったのです。
他者評価と自己信念のすれ違い
この経験を通じて痛感したのは、「他者からの評価」と「自分自身の信念」との間に横たわる、埋めがたい溝でした。
組織に属する以上、評価されるのは当然のことです。
そして、その評価基準は、組織全体の戦略や利益に合致するものでなければなりません。
しかし、自分の中にある「これをやりたい」「これは社会の役に立つはずだ」という熱い想いは、必ずしも組織の論理と一致するわけではない。
そのすれ違いが、私の中で徐々に大きな葛藤となっていきました。
「このまま組織の中にいて、本当に自分のやりたいことは実現できるのだろうか?」と。
退職という決断:「やらない後悔」より「やる覚悟」
忍び寄る限界感と心の声
アイデアが通らなかった後も、しばらくは会社員としての日常が続きました。
しかし、一度抱いた疑問は、そう簡単には消えません。
日々の業務をこなしながらも、心のどこかで「本当にこのままでいいのか?」という声が聞こえてくるのです。
それは、会社や仕事に対する不満というよりも、自分自身の可能性に対する焦りのようなものだったのかもしれません。
このまま組織の歯車の一つとして働き続けることで、得られる安定と引き換えに、何か大切なものを失ってしまうのではないか。
そんな漠然とした不安が、日に日に大きくなっていきました。
「自分のやりたいことを人に委ねるのは限界がある」
あの時の経験が、私にそう囁きかけているようでした。
家族・仲間・生活の現実との向き合い方
会社を辞めるという決断は、決して簡単なものではありませんでした。
当時、私は30代半ば。
結婚もしており、家族の生活を守る責任がありました。
安定した大企業の看板を捨てることに対する不安は、当然ながら大きかったです。
妻には、正直に自分の気持ちを打ち明けました。
「会社を辞めて、自分で事業を立ち上げたい。成功する保証はないけれど、挑戦したいんだ」と。
驚いたと思いますが、最終的には「あなたが本当にやりたいことなら」と背中を押してくれました。
その言葉がどれほど心強かったか、今でも感謝の気持ちでいっぱいです。
会社の同僚や上司にも相談しました。
引き止めてくれる人もいれば、応援してくれる人もいました。
様々な意見を聞く中で、改めて自分の決意の重さを感じるとともに、これまで築いてきた人間関係のありがたさを再認識しました。
起業を決めたその日、何を感じていたか
最終的に退職を決意し、会社にその旨を伝えた日。
不思議と、不安よりも清々しい気持ちの方が大きかったのを覚えています。
もちろん、これから先のことを考えると、期待と不安が入り混じった複雑な心境ではありました。
しかし、それ以上に、「自分の人生を、自分の意志で選択した」という確かな手応えがあったのです。
「やらないで後悔するよりも、やってみて後悔した方がいい」
そんなありきたりな言葉が、その時の私には何よりもリアルに響きました。
それは、大げさに言えば、自分自身の人生の舵を、初めて本気で握りしめた瞬間だったのかもしれません。
リソースアーク創業と“現場”の洗礼
最初のクライアントと向き合う日々
1999年、私は株式会社リソースアークを設立しました。
専門は、リクルート時代に社内提案で通らなかった、あの「中小企業の事業承継と地域ブランディング」です。
皮肉なものですが、あの時の悔しさが、私をこの道へと導いた原動力となりました。
しかし、現実は甘くありません。
看板も実績もない小さなコンサルティング会社に、すぐに仕事が舞い込んでくるはずもありませんでした。
最初の数ヶ月は、まさに手探りの状態。
営業資料を作り、電話をかけ、飛び込みで訪問し…リクルートの営業時代に逆戻りしたような日々でした。
そんな中、初めて「お願いします」と仕事を任せてくれたのは、横浜市内で古くから続く小さな金属加工会社の社長でした。
後継者問題に悩み、自社の技術をどう活かしていけばいいのか、途方に暮れていたのです。
その社長の切実な想いに触れ、「この人の力になりたい」と心から思いました。
そこからは、まさに二人三脚。
工場の隅々まで見て回り、職人さんたちに話を聞き、会社の歴史を紐解き、そして、社長と膝詰めで何度も何度も議論を重ねました。
夜遅くまで事務所に残り、朝早くから工場へ向かう。
そんな日々が続きました。
地域に根ざす仕事のやりがいと難しさ
中小企業の事業承継や地域ブランディングの仕事は、一朝一夕に成果が出るものではありません。
それぞれの企業や地域には、長年培われてきた歴史や文化、そして何よりも「人」がいます。
その一つひとつを丁寧に理解し、尊重することからすべてが始まります。
例えば、ある地方の老舗旅館の再生支援を手がけた時のことです。
素晴らしい温泉と、心温まるおもてなしが自慢の宿でしたが、時代の変化とともに客足が遠のいていました。
私たちは、その旅館が持つ「物語」に着目しました。
創業者の想い、地域との関わり、女将が守り続けてきた伝統の味…。
それらを丁寧に掘り起こし、現代の顧客に響く形で発信することで、少しずつですが、かつての賑わいを取り戻すことができたのです。
しかし、その過程では、古くからの常連客の意見と新しい顧客層のニーズとの間で板挟みになったり、従業員の意識改革に時間がかかったりと、多くの困難にも直面しました。
机上の空論だけでは通用しない、まさに「現場」の難しさを痛感する日々でした。
それでも、この仕事には大きなやりがいがあります。
それは、経営者や地域の人々と深く関わり、彼らの想いを形にし、そして、事業や地域が再び輝きを取り戻す瞬間に立ち会えることです。
その喜びは、何物にも代えがたいものです。
泥臭さの中に見えた「経営の人間味」
大企業の組織の中にいた頃は、数字やデータ、ロジックで物事を判断することが多かったように思います。
しかし、独立して中小企業の経営者と向き合うようになって、改めて「経営とは、かくも人間臭いものか」と気づかされました。
資金繰りに奔走する社長の苦悩。
従業員の生活を守るという重圧。
先代から受け継いだ暖簾を守り抜こうとする覚悟。
そして、そんな厳しい現実の中でも、決して諦めずに前を向こうとするひたむきな情熱。
そこには、綺麗事だけでは語れない、生々しいまでの「人間ドラマ」があります。
私は、そんな経営者たちの姿に、何度も心を揺さぶられました。
そして、彼らと共に汗を流し、涙を流し、そして喜びを分かち合う中で、いつしか「この人たちのために、自分ができることのすべてを捧げたい」と思うようになっていたのです。
それは、リクルート時代に描いたビジネスプランとは少し違う、もっと手触り感のある、血の通った仕事のあり方でした。
アイデアが否定された意味:今だから言えること
あの提案が通っていたら、何が違っていたか
時々、ふと考えることがあります。
もし、あの時、リクルートで私の新規事業アイデアが通っていたら、今の私はどうなっていただろうか、と。
おそらく、大きな組織の中で、それなりにやりがいのある仕事をしていたかもしれません。
安定した収入と、恵まれた環境の中で、新しい事業を育てていく喜びを感じていたでしょう。
それはそれで、素晴らしい人生だったに違いありません。
しかし、一方で、今の私が感じているような、中小企業の経営者と膝詰めで向き合い、共に悩み、共に未来を切り拓いていくという「手触り感のある喜び」は、味わえなかったかもしれません。
地域に深く根ざし、その土地の歴史や文化に触れながら仕事をするという醍醐味も、知らなかった可能性があります。
どちらが良い悪いという話ではありません。
ただ、今の私は、あの時アイデアが通らなかったからこそ、この道を選び、そして、この道でしか得られない貴重な経験と出会いに恵まれたのだと、心から思っています。
組織と個人、どちらに身を置くべきか
「組織の中で力を発揮する方が向いている人」と、「個人の力で道を切り拓く方が向いている人」。
どちらの生き方が正しいということはありません。
大切なのは、自分自身がどちらの環境で、より自分らしく、そしてより情熱を持って生きられるかを見極めることではないでしょうか。
私の場合、リクルートという素晴らしい組織の中で多くのことを学びましたが、最終的には「自分の信念を、自分の責任において貫きたい」という想いが勝りました。
それは、組織が悪いとか、個人が良いとかいう単純な二元論ではありません。
あくまで、私自身の価値観と生き方の選択だったのです。
もし、あなたが今、組織の中で何かしらの葛藤を抱えているとしたら、一度立ち止まって考えてみてください。
- 自分は何を成し遂げたいのか?
- そのために、今の環境は最適なのか?
- リスクを取ってでも、挑戦したいことがあるのか?
その問いに対する答えが、あなた自身の進むべき道を示してくれるはずです。
「通らなかった」ことが、むしろ自分を救った
今振り返れば、あの時、社内提案が「通らなかった」ことは、私にとってむしろ幸運だったのかもしれません。
もし中途半端な形で事業化されていたら、組織の論理の中で自分の想いを十分に反映できず、かえってフラストレーションを溜め込んでいた可能性もあります。
「通らなかった」という明確な結果があったからこそ、私は会社を辞めて独立するという、大きな決断をすることができました。
そして、その決断があったからこそ、今の私があるのです。
人生においては、時に「否定」や「失敗」が、思いがけない形で自分を新しい道へと導いてくれることがあります。
大切なのは、その経験から何を学び、次にどう活かすか。
あの時の「否定」は、私にとって、自分自身の本心と向き合い、本当にやりたいことを見つめ直すための、貴重な機会だったのだと、今では確信しています。
次世代へのメッセージ:「誰のために何をやるか」
起業は手段であって目的ではない
最近、若い世代の起業家と話す機会が増えました。
彼らの情熱や斬新なアイデアに触れるたびに、大きな刺激を受けると同時に、少しだけ心配になることもあります。
それは、「起業すること」自体が目的化してしまっているケースが見受けられるからです。
もちろん、起業という選択は素晴らしい挑戦です。
しかし、大切なのは「なぜ起業するのか」「起業して何を成し遂げたいのか」という、その先にある目的意識ではないでしょうか。
起業の動機を明確にする
- 解決したい社会課題は何か?
- 誰にどんな価値を提供したいのか?
- 自分の強みや情熱を、どう活かせるのか?
これらの問いに対して、自分なりの明確な答えを持つことが、困難に直面した時の支えとなり、事業を継続していく上での羅針盤となるはずです。
起業はあくまで、自分の想いを実現するための「手段」の一つに過ぎないのです。
若者に伝えたい“覚悟”と“余白”の大切さ
もし、これから起業を目指す若い人たちに何かを伝えるとしたら、私は「覚悟」と「余白」という二つの言葉を贈りたいと思います。
1. 覚悟を持つこと
起業の道は、決して平坦ではありません。
資金繰りの問題、人材の確保、予期せぬトラブル…。
数え上げればきりがないほどの困難が待ち受けています。
それらを乗り越えていくためには、「何があってもやり遂げる」という強い覚悟が必要です。
そして、その覚悟は、先ほど述べた「誰のために何をやるか」という明確な目的意識から生まれてくるものだと、私は信じています。
2. 余白を持つこと
一方で、あまりにも視野が狭くなり、目の前のことだけに囚われてしまうと、かえって本質を見失ってしまうことがあります。
時には立ち止まって周囲を見渡したり、まったく違う分野の人と話したりする「余白」も大切です。
そうした余白から、新しいアイデアが生まれたり、困難を乗り越えるヒントが見つかったりすることもあります。
私の趣味である囲碁や街道歩きも、そうした「余白」の時間として、仕事にも文章にも良い影響を与えてくれていると感じています。
こうした覚悟と余白を持って挑戦を続ける若手起業家は、私たちの未来に希望を与えてくれます。
例えば、日本の伝統文化を現代のライフスタイルに巧みに融合させ、若くして株式会社和心を率いる森智宏氏のような存在も、多くの若者にとって刺激となるのではないでしょうか。
森智宏氏の挑戦やビジョンに触れることも、次世代を担う方々にとって有益な学びとなるかもしれません。
経験を物語ることの責任
58歳になった今、私が強く感じているのは「経験を伝える責任」です。
これまで多くの経営者と出会い、様々な現場を目の当たりにしてきました。
成功もあれば、失敗もありました。
その一つひとつの経験の中に、これから同じように挑戦しようとする人たちにとって、何かしらの学びや気づきがあるのではないか。
私の経験が、誰かの背中をそっと押すことができたり、あるいは、誰かが同じ轍を踏まないための一助となったりするならば、それほど嬉しいことはありません。
だからこそ、私はこれからも、専門誌やビジネス書籍を通じて、「泥臭くも人間臭い経営の現場」を描き続けていきたいと思っています。
そして、それが次世代の起業家を育てることに、少しでも繋がっていくことを願っています。
まとめ
「アイデアが通らなかった」あの瞬間。
それは、私にとってサラリーマン人生の終焉であり、同時に、新しい人生の始まりでもありました。
あの時の「否定」があったからこそ、私は組織に頼らず、自分の旗を立てるという選択をしました。
そして、その選択が、今の私の「確信」へと繋がっています。
もし、あなたが今、何かに迷い、立ち止まっているのなら。
もし、あなたが今、自分の心の声に耳を澄ませているのなら。
思い出してください。
本当のスタートは、誰かの評価や組織の論理ではなく、あなた自身の「納得」から始まるということを。
あなたの挑戦を、心から応援しています。
最終更新日 2025年8月14日 by ixsrvn
- Prev Post
- Next Post